将来に備える生前整理としての墓じまい~家族に負担をかけないために~

人生の終わりを見据えて、いま「墓じまい」を選ぶ人が増えています。背景には少子高齢化や家族構成の変化、供養の価値観の多様化があります。将来、家族に負担をかけず、自分らしい形でご先祖を敬う。
この記事では、生前整理としての墓じまいのメリットや流れ、注意点をわかりやすく解説します。
なぜ今、墓じまいを考える人が増えているのか
少子高齢化と継承者問題
近年、少子高齢化の影響により、お墓を継ぐ人がいないという家庭が増えています。子どもがいない、または遠方に住んでいて継承が難しいといった事情から、墓じまいを検討する方が増えているのです。
特に都市部では、実家に戻る予定のない子ども世代が増え、無縁墓になるリスクも現実味を帯びています。
ご先祖を大切に思うからこそ、墓じまいという選択肢を前向きに考える人が増加しているのです。
生活スタイルの変化と宗教観の多様化
核家族化や転勤、海外移住などライフスタイルが多様化したことで、昔のように同じ墓を代々守るという考え方が難しくなってきました。
また、宗教に対する価値観も変化しており、「形式にとらわれず、自分らしい供養をしたい」と考える方も増えています。
お墓を持たず、樹木葬や自宅供養といった新たな選択肢に関心が高まっているのも、現代ならではの流れといえるでしょう。
生前整理の一環としての墓じまいのメリット
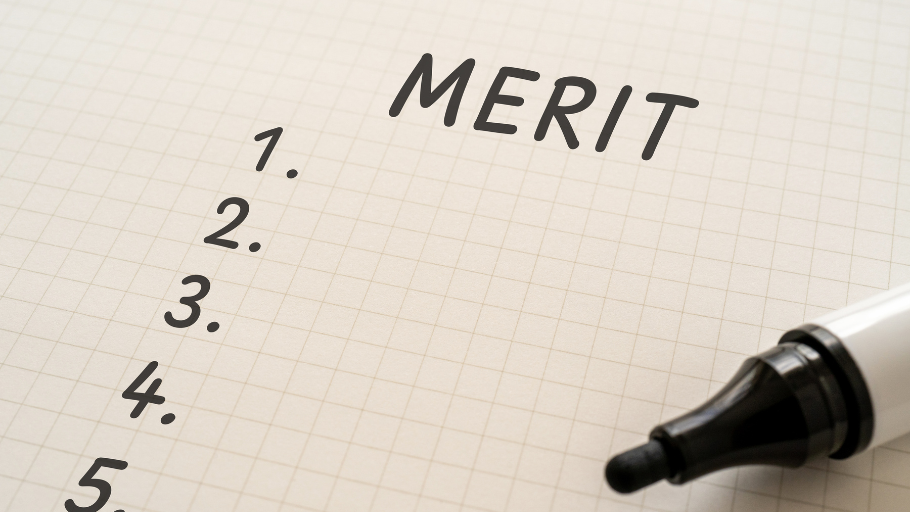
家族の負担軽減とトラブル防止
墓じまいを生前に行うことで、残された家族への精神的・金銭的な負担を大きく減らすことができます。
死後に突然お墓の管理や移転を任された家族は、対応に悩み、親族間で意見が分かれるケースも少なくありません。特に兄弟姉妹間で考え方が食い違うと、深刻なトラブルになることも。
あらかじめ自分の意思で準備を整えておけば、こうした混乱を防ぎ、家族が安心して故人を見送る環境を整えることができます。
費用と時間を自分でコントロールできる
生前に墓じまいを進める最大のメリットは、自分で計画を立て、費用やスケジュールを調整できる点です。亡くなった後では、家族が急いで対応しなければならず、納得のいかない業者に依頼してしまうケースもあります。
生前整理の一環として取り組めば、複数の業者に見積もりを取り、比較検討しながら無理のない予算内で進めることが可能です。心にも時間にも余裕を持って、自分の価値観に合った形で選択できるのは、大きな安心材料となります。
墓じまいの流れと必要な手続き
まずはお寺や霊園との相談から
墓じまいを始めるにあたって最初に行うべきなのが、現在の墓地を管理しているお寺や霊園への相談です。
勝手に撤去を進めることはできず、事前に合意や了承を得ることが重要です。特に寺院墓地の場合、檀家制度や宗教的なしきたりが関係してくるため、話し合いの姿勢を大切にすることが求められます。
丁寧に意向を伝え、必要な手順を確認することで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
行政手続きと改葬許可証の取得
墓じまいでは「改葬許可証」という公的書類が必要になります。これは、現在のお墓から遺骨を別の場所へ移す際に、自治体が発行する許可証です。
まずは現在の墓地管理者から「埋蔵証明書」を受け取り、それをもとに新しい納骨先が決まっていることを証明して、役所で申請を行います。
申請書類に不備があると許可が下りないため、各自治体の規定をよく確認しながら、丁寧に手続きを進めることが大切です。
遺骨の行き先と供養方法の選択
墓じまい後に遺骨をどこに納めるかは、最も大切な選択の一つです。永代供養墓や納骨堂、樹木葬など、現代には多様な供養方法があります。
自分や家族の価値観、宗教的な考え方に合った形を選ぶことが求められます。また、遠方の墓地に遺骨を移す場合には、交通手段やアクセスのしやすさも考慮しておきたい点です。
心を込めて供養できる方法を選ぶことで、故人の方への思いを丁寧に引き継ぐことができます。
墓じまいにかかる費用と相場感
主な費用項目と目安
墓じまいにかかる費用は大きく分けて「墓石の撤去費用」「遺骨の移送費」「新たな納骨先の費用」「改葬手続きに関わる諸費用」などがあります。
例えば、墓石の撤去には10万円〜30万円ほどが目安で、広さや場所によって上下します。永代供養墓などへの納骨費用は10万円〜50万円ほどが一般的です。
合計としては30万円〜100万円程度になることが多いため、事前に内訳を把握しておくことが大切です。
費用を抑えるためのポイント
墓じまいの費用を抑えるには、複数の業者に見積もりを依頼して比較することが有効です。
また、自治体によっては改葬に関する補助金制度がある場合もあり、そうした情報を活用することで負担を軽減できます。
納骨先も、都心部より地方のほうが費用を抑えられる傾向にあります。必要以上に豪華なプランを選ばず、自分や家族の意向に合った無理のない供養スタイルを選ぶことが、満足度とコストの両立につながります。
トラブルを避けるための注意点

親族間の合意形成
墓じまいは、感情が絡むデリケートな問題であるため、親族間での十分な話し合いが欠かせません。事後報告で進めてしまうと「相談もなしに勝手に決めた」と不満が噴出し、深い溝を生むことがあります。
特に兄弟姉妹や親戚が関係する場合は、背景や立場の違いにも配慮しながら丁寧に説明しましょう。理解が得られるまで時間がかかることもありますが、信頼関係を壊さないための大切なステップです。
墓地管理者との調整
墓地や霊園の管理者との調整は、墓じまいの成否を左右する重要な行程です。墓石を撤去する際には、管理規約や契約内容に沿った手続きが必要で、事前の確認を怠るとトラブルになることもあります。
寺院墓地では、檀家を離れる場合の「離檀料」が発生するケースがあるため、費用面も含めて早めに相談しておくことが大切です。穏やかな話し合いを心がけることで、円満な進行が期待できます。
宗教的・精神的な配慮も忘れずに
墓じまいは物理的な作業だけでなく、故人の供養という精神的な側面も大切にしたいものです。
お墓にはご先祖や家族の想いが込められているため、移転や撤去にあたっては法要やお焚き上げなど、供養の儀式を行うことが望ましいと思います。
また、宗派や地域によって考え方や慣習が異なるため、無理なく受け入れられる方法を選ぶことが必要です。心を込めた対応が、家族みんなの納得と安心につながります。
墓じまい後の遺骨の供養方法いろいろ
永代供養墓・納骨堂・樹木葬などの選択肢
墓じまい後の供養方法として、多くの方が選んでいるのが永代供養墓や納骨堂、樹木葬といった新しいスタイルです。
永代供養墓は、管理者が継続して供養してくれるため、継承者がいない方にも安心です。納骨堂は都心部を中心に増えており、室内型で天候に左右されない利便性があります。
自然に還ることを望む方には、墓石を建てない樹木葬も人気です。それぞれに特徴があるため、自分に合った方法をじっくり検討しましょう。
自宅供養や手元供養という選択も
近年では、遺骨を自宅で保管する「自宅供養」や、骨の一部を小さな容器に収める「手元供養」を選ぶ人も増えています。
これらは形式にとらわれず、故人を日常の中で身近に感じたいという想いから選ばれることが多い供養方法です。
ただし、保管方法や将来的な扱いについては家族で十分に話し合うことが必要です。手軽さの一方で、法的な扱いや他者の理解を得る難しさもあるため、事前に確認しておくことが安心につながります。
最後に~「想い」をつなぐ墓じまいを考える
墓じまいは、単なる片付けや手放しではなく、「想いをどう受け継ぐか」を考える大切な機会です。
ご先祖への感謝や家族のつながりを形に残すために、自分らしい供養の形を選ぶことが求められています。準備を早めに始めることで、心にも時間にも余裕が生まれ、家族と丁寧に向き合うことができます。
これからの時代に合った供養のあり方を見つけ、次の世代へ安心してバトンを渡す。これこそが、現代の墓じまいの意義なのかもしれません。
リリーフのご案内
創業60年のリリーフは社内研修を終えた専属スタッフが対応し、高齢者やご遺族の負担を軽減するため、安心・丁寧な遺品整理を全国で展開しています。私たちは、お客様一人ひとりの「心の整理」をサポートし、「ありがとう」の感謝の気持ちが溢れる、温かい社会の実現を目指してまいります。
部屋や実家の不用品処分・遺品整理・生前整理は、お片付け専門サービス「Relief(リリーフ)」 にお任せください。
ワンストップ対応
仕分け・搬出・リユース・処分まで自社一貫。現地無料見積り後の追加費用なしで安心です。
- 環境と家計にやさしいリユース
海外への再利用ネットワークで処分費用を 20%〜40%削減(※家具の状態によります)。 - 立会い不要・遠方物件もOK
遠隔地の実家や空き家でも、カギをお預かりしてスピーディーに作業を完了します。 - 空き家管理サービスも併設
定期換気・簡易点検・郵便物確認など、活用方法が決まるまでの維持管理もサポート。
引っ越し前の不用品処分から、実家じまい・施設入居準備まで——
リリーフ が“片付けのストレス”を丸ごと解決します。
相談・見積りは 完全無料。「SBI証券からの紹介」とお伝えください。
フリーダイヤル 0120-112-089 または公式サイト・LINEから、ご連絡くださいませ。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。

株式会社リリーフ
- 対応地域
- 関東、宮城、新潟、東海、関西
- 営業時間
- 午前9:00〜午後6:00
- アクセス
- https://relief-company.jp/shop/
- 得意分野
- 遺品整理、不用品処分など家財道具や不用品の整理・処分