相続の相談、市役所での無料相談はどこまで対応?専門家との違いは? (弁護士ドットコム株式会社 2025.6.12)
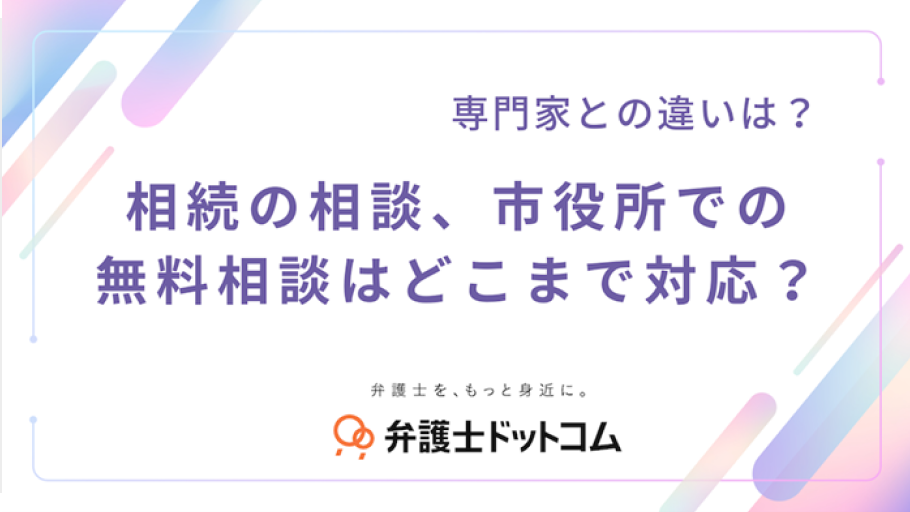
相続が発生すると、多くの手続きが必要になります。これらの手続きは複雑で、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。また、相続人の間で意見が対立し、トラブルに発展するケースもあります。
こうした相続に関する疑問や悩みを抱えたとき、どこに相談すればよいのでしょうか。頼りになる相談先として、市役所などの公共機関が提供する無料相談窓口や、弁護士・税理士などの専門家が挙げられます。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切に活用することが、スムーズな相続手続きへの第一歩となります。
この記事では、相続に関する相談先について、市区町村役場などの公的機関が提供する無料相談窓口から、弁護士、司法書士、税理士といった各専門家まで、それぞれの役割や特徴、相談可能な範囲を解説します。
無料で相談できる公的機関窓口
まずは気軽に利用できる公的機関の窓口への相談を検討しましょう。市区町村役場や法テラス等では無料または低コストで弁護士等に相談でき、問題点を整理できます。本格的な依頼の前段階として一般的な助言を受けることで、対応の方向性を見定めるのに役立ちます。
1.市区町村役場
多くの市区町村役場では、定期的に弁護士や司法書士などの専門家による無料法律相談会を実施しています。相続に関する一般的な疑問や、手続きの進め方についてアドバイスを受けることができます。
- 相談内容: 遺産分割の方法、遺言書の作成や効力、相続放棄などに関する法律相談
- 利用方法: 実施日時や予約の要否は、お住まいの市区町村役場のウェブサイトや広報誌などで確認が必要です。対面相談が主ですが、電話相談に対応している場合もあります。
- 注意点: 相談時間や回数に制限がある場合が多いです(例:「1人30分まで」「年度内に1回まで」など)。すでに裁判所で訴訟や調停が進行中の問題は対象外になる場合があります。事前予約が必要な場合があります。相談担当の弁護士に、その場で事件解決を依頼したり、特定の弁護士を紹介してもらったりすることができないことがあるため、書類作成や手続きの代行が必要な場合には、別途弁護士事務所などに相談する必要があります。
2. 税務署
相続税に関する相談については、まず国税庁ホームページのチャットボットやタックスアンサーを利用することが推奨されています。これらは土日や夜間でも利用可能です。タックスアンサーでは、よくある国税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
もしチャットボットやタックスアンサーで解決しない場合は、電話相談センター(ナビダイヤル:0570-00-5901)に電話で相談することができます。電話相談センターでは、制度や法令等の解釈・適用、手続き案内などの相続税に関する一般的な相談について、国税局の職員等が対応しています。
具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど、チャットボット、タックスアンサー、電話相談センターでの解決が困難な相談については、所轄の税務署での対面相談が可能です。対面相談には、事前予約が必要です。
- 利用方法: チャットボットやタックスアンサーは国税庁ホームページにていつでもアクセス可能。電話相談センターは平日午前8時30分から午後5時00分まで。対面相談の事前予約は、所轄の税務署に電話をかけて行います。
- 注意点: 一般的な質問は、まずウェブサイトのチャットボットやタックスアンサーで確認してください。電話相談は、制度の解釈など一般的な内容が中心です。個別の具体的な事案に関する相談や、書類の確認が必要な場合は、税務署での対面相談(要予約)となります。
3. 法テラス(日本司法支援センター)
法テラスでは、経済的にお困りの方を対象に、弁護士や司法書士による無料の法律相談を受けることができます。相談だけでは問題が解決しない場合、弁護士や司法書士に依頼する際の費用を法テラスが立て替える制度を利用することもできます。
- 相談内容: 遺産分割の方法、遺言書の作成や効力、相続放棄などに関する法律相談
- 利用方法: 事前の予約が必要です。予約は電話または一部相談場所ではWebでも行えます。相談場所や相談方法は地域によって異なるため、相談を希望する法テラスの地方事務所ページでご確認ください。
- 注意点: 収入や資産が一定基準以下などの条件を満たす必要があります。予約時に収入(手取りの平均月収、賞与も含む)や資産(現金・預貯金)について聞かれます。
公的機関の無料相談の限界
無料相談は気軽に利用できる反面、相談時間や回数の制限、対応範囲の限界があります。相談できる範囲や、その後に継続的なサポートを依頼できるかどうかなど、仕組みをよく理解して利用しましょう。複雑な事案や相続人間で争いがある場合には、専門家への相談や依頼も検討しましょう。
専門家への相談・依頼(有料)
無料相談で解決が難しい場合や、より踏み込んだサポートが必要な場合は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった専門家への相談・依頼を検討しましょう。費用は発生しますが、個別の状況に合わせた具体的な手続きの代行や紛争解決に向けた交渉など、充実したサポートが期待できます。
事務所によっては、複数の専門家が所属していたり、他の専門家の事務所と提携したりして、ワンストップでサービスを受けられる場合もあります。
1.弁護士
相続に関するほぼ全ての法律事務を取り扱うことが認められているのが弁護士です。
- 依頼できる業務: 相続人・相続財産の調査、遺産分割協議の交渉代理、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判の代理、遺留分侵害額請求、相続放棄の手続き、相続税申告(※税理士資格を持つ場合や提携税理士がいる場合)など、相続に関するほぼ全ての業務。
- 特に強みを発揮するケース: 相続人間で意見が対立している、遺産分割協議がまとまらない、調停や審判に発展しそう(または発展している)、遺産の範囲や評価に争いがある、遺留分を請求したい(または請求されている)など、法的な紛争性が高いケース。
- メリット: 依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や、裁判所での手続き(調停・審判)を全て任せることができます。複雑な手続きも一任できるため、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます。
- 注意点: 他の専門家と比較して費用が高くなる傾向があります。
2.司法書士
司法書士は、不動産登記や相続関連の書類作成を行うことができる専門家です。
- 依頼できる業務: 相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割や登記手続きに必要な範囲での相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続放棄に関する裁判所提出書類の作成支援など。
- 特に強みを発揮するケース: 相続財産に不動産が含まれており相続人間での争いがなく、主に登記手続きを依頼したい場合。
- メリット: 相続人間で争いがなく登記手続きがメインであれば、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。
- 注意点: 弁護士とは異なり他の相続人との交渉代理や、遺産分割調停・審判の代理人になることはできません(※認定司法書士は簡易裁判所での代理権がありますが、相続案件では対応範囲が限られます)。法的な紛争が生じた場合は対応できません。
3.行政書士
書類作成の専門家です。
- 依頼できる業務: 遺産分割協議書の作成、相続人調査、自動車の名義変更、預貯金の解約・名義変更に関する書類作成など。
- メリット: 比較的費用を抑えて書類作成を依頼できます。
- 注意点: 不動産の相続登記はできません。他の相続人との交渉代理や裁判所での手続き代理もできません。業務範囲が弁護士や司法書士と重なる部分が多く、登記が必要なら司法書士、紛争の可能性があるなら弁護士に依頼する方が、ワンストップで対応できる場合が多いです。
4.税理士
相続税に関する専門家です。
- 依頼できる業務: 相続税の計算・試算、相続税申告書の作成・提出、税務調査への対応、生前の相続税対策(贈与など)の相談。
- 特に強みを発揮するケース: 相続財産が多く相続税申告が必要な場合、相続税額を正確に計算したい場合、節税対策について相談したい場合。
- メリット: 相続税に関する専門的な知識に基づき、適正な申告や納税、節税に関するアドバイスが受けられ、手続きを依頼することもできます。
- 注意点: 相続税以外の相続手続き(遺産分割協議、登記など)や、法的な紛争解決は業務範囲外です。
専門家の選び方のポイント
- 相談内容: まず、自分が何を相談・依頼したいのか(手続き代行、交渉、調停・審判、登記、申告など)を明確にしましょう。
- 専門分野: 各専門家には得意分野があります。相続案件の実績が豊富な専門家を選びましょう。
- 相性: 無料相談などを利用して、実際に話してみて、信頼できるか、コミュニケーションが取りやすいかを確認することも重要です。
- 費用: 費用体系は事務所によって異なります。事前に見積もりを取り、納得した上で依頼しましょう。
5.銀行の相続手続きサービス
一部の銀行では、遺産整理業務として、相続財産の調査、遺産分割協議書作成のサポート、預貯金の解約・分配などの手続きを代行するサービスを提供しています。
- メリット: 窓口が一つで済む利便性があります。
- 注意点: 一般的に、専門家に直接依頼するよりも高額になる可能性があります。相続人間での争いや交渉が必要な案件は取り扱えません。不動産登記や税務申告を銀行自身が行うことができないため、不動産登記や相続税申告は別途、司法書士や税理士への依頼が必要になります。
まとめ
相続に関する悩みや手続きは、まず市区町村役場や法テラスなどの無料相談を活用してみて、基本的な情報を得ることが有効です。
相続人間で争いがある場合や、手続きが複雑で自分で行うのが難しい場合は、早期に専門家への相談・依頼を検討することが重要です。特に、法的な紛争解決が必要な場合は弁護士が適任です。不動産登記が中心なら司法書士、相続税申告が必要なら税理士といったように、依頼したい内容に応じて適切な専門家を選びましょう。
費用はかかりますが、専門家に依頼することで、時間的・精神的な負担を軽減し、法的に適切な手続きを進めることができます。初回相談を無料で行っている事務所も多いので、まずは気軽に相談し、費用やサポート内容を確認した上で、信頼できる専門家を見つけることをお勧めします。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
