徹底解説!上場株式の相続で気をつけるべきポイント (株式会社400F 2024.11.28)
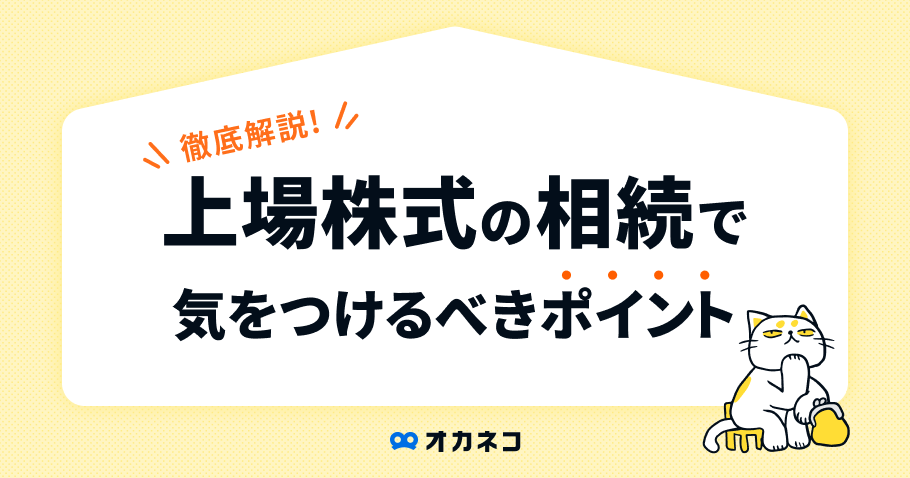
上場株式の相続税評価額

相続財産は預金ばかりとは限りません。故人の保有していた資産の種類により、相続税評価額の考え方は異なる点に注意して確認しましょう。
まずは上場株式を相続した場合の評価の方法について確認します。
株式の評価額は日々変動しています。このため、株価の急変による不利益を是正するために、相続税評価額は次の4つの中から最も低い価格で評価されます。
- 被相続人が死亡した日の終値
- 被相続人が死亡した月の毎日の終値の平均
- 被相続人が死亡した前月の毎日の終値の平均
- 被相続人が死亡した前々月の毎日の終値の平均
終値の平均がもっとも低い時点の株価を相続税評価の際に用いることにより、相続税評価額を減らし、相続税を節税することが可能になります。
また、被相続人が複数の銘柄の上場株式を保有していた場合、全ての株式を同じ時期で評価する必要はなく、その株式ごとに最も低い金額で評価することが可能です。
現預金とは異なり、変動資産であることから特有の評価方法がある点が株式の相続の特徴であることを覚えておきましょう。
株式の遺産分割方法
実際に株式を相続する場合の分割方法について見ていきます。
相続人が1人の場合は、株式や現金、不動産などを1人で全てを相続する手続きを進めるため特に問題はありませんが、相続人が複数人いる場合は注意が必要です。
相続人が複数人いる場合、相続財産である株式を分割する必要があります。
株式の分割方法は次の3種類があります。
①現物分割
株式をそのまま相続する方法です。被相続人が保有していた株数によっては、複数の相続人に均等に分けて相続することも可能です。被相続人が保有していたA株式10,000株のうち3,000株は甲さんに、7,000株は乙さんに、というように分割することも可能です。
ただし、株式の価格は常に動くため、その後の株価の推移次第では将来の資産評価が大きく変わる場合があります。相続人の間でのトラブルを避けるために、銘柄ごとに株数を均等に分割することも視野に入れておきましょう。
②換価分割
被相続人が保有していた株式を現金化し、その売却代金を相続人で分割する方法です。相続人全員が株式での継続保有を望まない場合などに有効です。現金化されることにより均等に分割が可能な点がメリットになります。
③代償分割
複数の相続人のうち1人が株式を相続し、その株式を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。将来の値上がりが期待できる場合に株式を売却する必要がない点はメリットと言えます。しかし代償金の用意が必要な点や、どの時点の評価額で代償金額を決めるかで相続人の間でトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
遺産分割協議では相続人同士でトラブルになるケースも少なくないため、生前に遺言書を作成しておくことも重要です。
株式売却時の所得税と取得費加算の特例

株式売却時の所得税
通常、株式を売却して利益が出た場合は、その譲渡所得(売却益)に対して課税されます。
相続により取得した株式を売却した場合も同様で、譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。株式の譲渡所得にかかる所得税・住民税は一律で20.315%となっています。
譲渡所得は、「売却金額-取得費」で求められますが、その取得費は被相続人の取得費を引き継ぐことになります。
相続により取得したときの評価額ではなく、被相続人が取得した金額となる点に注意が必要です。
※被相続人がNISA口座で取得した株式を相続した場合の取得費は、被相続人死亡日の終値を使用します。
被相続人が特定口座やNISA口座にて株式を保有している場合は、取得時の価格が証券会社にて管理されているため問題ありませんが、一般口座で保有している銘柄については取得価格がわからないケースも多くあります。証券会社にて保管されている顧客勘定元帳の取り寄せや、株主名簿管理人(信託銀行)への問い合わせで確認ができる場合もあるため、必要に応じて利用しましょう。
被相続人が取得した金額がわからない場合は、「売却代金の5%」を取得費とすることができます。しかし、この場合は「譲渡所得(売却益)=売却代金の95%」となるため、税負担が大きくなってしまう点に注意が必要です。
取得費加算の特例
相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合には、「売却した株式に対する相続税額」を取得費として加算できる特例があります。
これを「取得費加算の特例」といいます。
この特例を利用することにより、譲渡所得にかかる税負担を軽減することが可能です。
考え方としては、相続税額のうち、相続した財産の総額に占める譲渡した株式の評価額に相当する金額を取得費とします。具体例を見ていきましょう。
〈例〉
相続した財産の総額:1億円
譲渡した株式の相続税評価額:5,000万円
相続時に支払った相続税:500万円
当該株式の譲渡所得:1,000万円
取得費加算額=500万円×5,000万円/1億円=250万円
Ⅰ.取得費加算の特例を利用しない場合の譲渡所得にかかる税金
1,000万円×20.315%=2,031,500円
Ⅱ.取得費加算の特例を利用した場合の譲渡所得にかかる税金
(1,000万円‐250万円)×20.315%=1,523,625円
上記のように取得費加算の特例を利用することにより、税負担の軽減を図ることが可能であるため、株式を相続し売却を検討する場合は積極的に活用しましょう。
ただし、相続税の申告期限の翌日から3年以内に株式を譲渡しなくてはならない点、確定申告が必要な点には注意が必要です。
事前にできること
ここまで、一般的な株式の評価額と分割方法、相続した株式の売却について記載をしました。
続いて株式の相続を想定した場合に、相続人の負担を少しでも減らすために事前に行っておくとよいことについてご案内します。
①相続時の手続きについて
株式を相続する場合、相続人は被相続人が株式を保有している証券口座のある証券会社にて口座開設を行い、その株式を移管する必要があります。
このため、被相続人が複数の証券口座で株式を保有している場合は、同様に複数の口座を開設し各証券会社で相続手続きを行う必要があります。
相続手続きは証券会社以外にも各所で必要になるため、相続税申告までに取りまとめることを想定すると複数口座での手続きは相当の負担になる可能性が高いです。
株式での相続を想定する場合は、複数の証券会社での株式保有は避けたほうがよいでしょう。
②信託銀行の特別口座に株式を保有している場合
一般に、上場株式は証券会社にて保管がされていますが、まれに信託銀行の特別口座にて端株(単元未満株式)を保有している方がいます。2009年に行われた株式の電子化(株券の廃止)の際、端株や証券会社に預けていなかったタンス株が信託銀行の特別口座での預かりになっているなどのケースです。特別口座で株式を保有していた場合、相続発生時は証券会社での手続きとは別に、信託銀行での手続きが必要になります。相続人の負担になってしまう可能性も高いため、あらかじめ信託銀行の特別口座の保有の有無の確認、特別口座を保有している場合は証券会社への移管手続きをとっておくことをおすすめします。
③配当金の受取について
株式の配当金の受取方法は下記3種類あります。
- 証券会社口座に入金される「株式数比例配分方式」
- 銀行に振り込みがされる「一括振込方式」または「個別銘柄指定方式」
- 配当金受領証を金融機関の窓口まで持参し受け取る「配当金領収証方式」
このうち、被相続人が配当金を「配当金領収証」により受け取っていた場合は、相続発生以後に支払いのあった配当金については受取のための手続きが必要になります。また、受取手続期限内に手続きをしない場合は信託銀行にて相続手続きが必要になります。こちらも、相続人の手続きが増え負担が大きくなってしまう可能性が高いため、配当金が証券会社口座に入金される「株式数比例配分方式」に変更しておくことをおすすめします。
まとめ
株式の相続税評価の仕方や、相続後の売却等についての知識があれば節税につなげることができます。制度を上手に活用し、また、事前に対策をすることでスムーズに株式を引き継ぐことができるようにしておきましょう。
加えて、相続税の納付については以下の点にも注意しておきましょう。
相続税の納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。
株式の売却資金で相続税を支払う場合は、分割協議が納付期限までにまとまらない、株価が想定外に下がってしまい売却ができない等により充当できない可能性もあります。
一定額は現預金で資産を保有しておく、生命保険を活用するなど、現金化しやすい資産を併せて用意しておくことも検討するとよいでしょう。
また、検討に際して悩むことがあれば、ぜひ『オカネコ』をご活用ください。
『オカネコ』は、家計改善、資産運用、保険などお金に関するさまざまなアドバイスをワンストップで無料相談できる国内最大級のプラットフォームであり、どんな立場の方にも有効な「お金の問題解決」の機会を提供しています。
相続に関するお金の悩みも、お金のプロに何度でも無料で相談できます。
現金化しやすい資産をどのように用意したらよいか分からない、相続で得たお金を資産運用に回したいけど、何をすればよいかわからない方も、ぜひオカネコにご相談ください。
▼オカネコへのご相談はこちら
https://okane-kenko.jp/planner/2794?exclusive
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
