争族とならないために考えておきたい遺産分割対策のポイント (株式会社400F 2025.2.14)
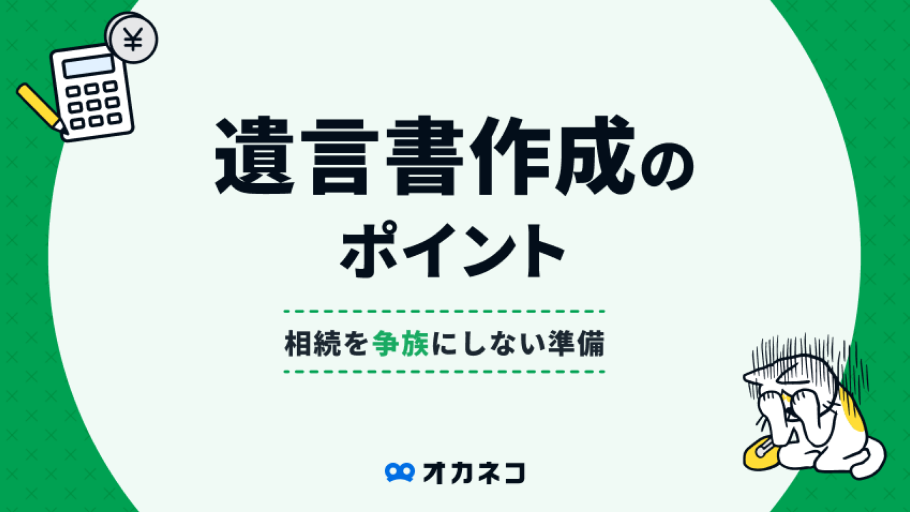
相続対策は必要?
相続対策と聞いて皆様どのようなイメージをお持ちでしょうか。
「自分はそんなに資産があるわけでもないから必要ない」
「子供たちも仲が良いし、しっかりしているので心配していない」
「今は元気だから病気になってからでよいと思っている」
「親の相続のことは心配だけれど、自分からは聞きにくい」
そのような方も多いのではないでしょうか。
本当に自分や家族の相続について注意すべき点はないのか、一度確認していただくことをお勧めします。
相続財産を受け取る権利のある人が複数名いる場合、その全員が100%同じ意見でまとまるのは非常に難しいかと思われます。
生前たくさん面倒を見ていたので自分は多くもらいたいと考える人や法定相続分に従って平等に分けるべきと考える人、また自分は相続財産の分け方に納得しているのに家族から反対されて困る人などもおり、様々な考えが交錯した結果「争族」となってしまう場合があります。残されたご家族が困らないようにするためにも、まずは遺産分割対策において押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。ここでは相続人の範囲や法定相続分について確認した上で、遺言の効果や作成時の注意点、特に準備しておくべき人についてご案内していきたいと思います。
遺産はどうやって分ける?~遺産分割対策~

法定相続分とは
まず、相続人の範囲や法定相続分についてお話ししていきます。
相続人の範囲は民法で定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人については第一順位:死亡した人の直系卑属(子)、第二順位:死亡した人の直系尊属(父母・祖父母等)、第三順位:死亡した人の兄弟姉妹の順序で相続人になります。
また、法定相続分とは民法で定められた法定相続人が有する相続割合を指します。法定相続分は相続人で遺産分割の合意ができなかった時の遺産の持ち分であり、必ずこれに従って遺産分割をしなければならないわけではありません。
法定相続分は相続人の構成によって異なります。相続人が配偶者と子供の場合は配偶者2分の1・子供2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となります。なお、子供や直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、決定する順位のなかで原則として均等に分けます。
遺言の効果
相続財産を承継するにあたり、遺言の有無がポイントとなります。
遺言がない場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって相続財産を自由に分割することができます。この際全員の合意が必要となります。遺産分割協議で話がまとまらない場合は法定相続分で分割を行いますが、家庭裁判所の調停や審判の手続を申し立てることで裁判所に判断してもらうこともできます。争族となる大きな要因がこの遺産分割協議にあります。
相続人同士のトラブル防止に加え、被相続人本人の想いを実現するために有効となるのが遺言です。遺言は法定相続に優先します。大切に築き上げてきた財産を自分の想いに沿って分けることができます。
遺言作成における注意点

ただ、遺言を作成するのにもいくつか注意点があるため、確認しておきましょう。
分割方法 ~遺留分とは~
法定相続人には、最低限保証された遺産取得分として遺留分があります。
具体的には、相続人が配偶者と子供の場合は配偶者に4分の1・子供に4分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者に3分の1・直系尊属に6分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者のみ2分の1(兄弟姉妹はなし)が認められています。
遺言で財産配分を自由に決定することはできますが、特定の人に財産を集中させる場合は遺留分を侵害する可能性もあるため注意が必要です。
遺留分を無視した遺言の作成自体は可能ですが、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
遺言の作成方法 ~自筆証書遺言と公正証書遺言~
遺言は遺言者が亡くなったときに初めて効力を生じます。せっかく作成した遺言が無効とならないよう、遺言作成のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。それぞれ概要やメリットデメリットを確認していきます。
【自筆証書遺言】
文字通り、遺言を自書する形式の遺言です。財産や相続人を洗い出し、日付・氏名とともに遺言全文を正確に記載し押印します。
財産目録に関してはパソコンで作成、もしくは通帳のコピー等を添付することも可能です。
自筆証書遺言作成後の保管方法は二通りあります。
以前は自宅等で保管する方法のみでしたが、法務局でも保管することができるようになりました(自筆証書遺言書保管制度)。自宅で保管する場合、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要があります。この検認とは、遺言の有効無効を判断するものではなく、遺言書の形状や加除訂正の状態等遺言書の内容を明確にして偽造を防止するためのものです。
一方、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、所定の様式にて遺言書を作成し法務局にて申請を行います。保管の申請には申請1件(遺言書1通)につき3,900円の手数料がかかりますが、相続発生時裁判所の検認は不要となります。なお、法務局では遺言書の内容に関しての相談はできないため、相談したい場合は弁護士等の法律の専門家等に相談する必要があります。
自筆証書遺言のメリットは、遺言者本人の意思で自由に作成・変更ができ、コストが抑えられる点にあります。一方、デメリットとしては遺言の内容が不明確である場合やその他の事情により相続人との間で争いになる可能性を含んでいます。また遺言書を自宅で保管する場合は、相続人に偽造改ざんされるおそれや、いつまでも発見されない可能性があることに加え、裁判所の検認も必要となります。こちらのデメリットを解消するために新設されたのが自筆証書遺言書保管制度です。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は法律の専門家(公証人)が作成し保管する方法です。公証役場にて2名以上の証人と公証人が立ち合いのもと遺言の趣旨を口述し、それが遺言者の真意であることを公証人が確認した上で文章にまとめます。
それを遺言者・証人へ読み聞かせ内容を確認してもらった上で公正証書遺言として作成します。遺言内容について公証人に相談しアドバイスを受けることも可能です。公正証書遺言のメリットは、公証人により作成されるため無効になるおそれがなく信頼性が高いこと、公証役場で保管されるため発見されないリスクが低い、隠ぺいや改ざんされない等が挙げられます。
一方デメリットとしては、費用がかかる点、証人が必要である点などがあります。証人2名は遺言者が手配することができますが、推定相続人や遺贈を受ける人、またその配偶者や直系血族、未成年者はなることができない等の制約があります。この証人は公証役場にて紹介を受けることも可能です。
自分で調べながら自筆での作成が可能な方は自筆証書遺言、プロのアドバイスに基づき信頼度の高いものを作成したい意向の方は公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
遺言を作成した方がよいケース
ここまで遺言を作成する上での注意点をお伝えしてきましたが、最後に遺言を作成した方がよいケースについて今回は二つご紹介していきます。
【ケース①】子供のいない夫婦の場合
子供がいなくて、兄弟姉妹がいる(両親は他界)場合の法定相続分について考えてみましょう。その場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。配偶者に全財産を渡すことができると思っている方もいらっしゃいますが、遺言がない場合は配偶者と兄弟姉妹(他界している場合はその甥や姪)が遺産分割協議を行う必要があります。兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を配偶者に渡したいとお考えであれば遺言の作成が有効です。
ここで予備的遺言についても触れておきます。先程の例で仮に配偶者に全財産を残したいと考えていても、自分よりも先に配偶者が亡くなってしまう可能性もあります。そういった可能性も考慮して、「万一、遺言者よりも配偶者が先に亡くなっていた場合は○○を姪に、△△を甥に相続させる」等を記載したものが予備的遺言です。これにより、「配偶者が既に亡くなっていた場合は同じく年齢の近い兄弟姉妹ではなく甥姪に渡したい」等の意向を添えることもできます。
【ケース②】不動産を所有している場合
不動産は物理的に分けることが困難なため、トラブルに発展するケースが多いです。
複数の不動産を保有している場合、どの不動産を誰が相続するかによって揉めることがあります。収益不動産を保有されている場合、不労所得を得たいというお考えもあれば、管理をするのが面倒なので保有したくないというお考えもあるかと思います。
また、自宅しか所有していない場合であっても注意が必要です。例えば相続人が二名で一方のみが不動産を相続する場合、不動産を相続する人はその分預金の相続分が少なく納税資金の確保が難しくなってしまう可能性があります。また、不動産を法定相続分に従い分けようとすると、不動産は相続人の共有名義となります。共有名義の不動産を売却しようとする場合、名義人全員から同意を得る必要があります。意見が一致すればよいですが、「想い入れがあるので売却したくない」「自分が住みたい」「人に貸して賃料収入を得たい」など意見が食い違い、売却できないままになっているというお話もよく耳にします。財産の保有者の意思で遺言によって決めておくことによりご家族間の争いを防ぐことができるかもしれません。また、争いを防ぐためにも不動産はお元気なうちに処分される方もいらっしゃいます。(不動産のまま相続する方が相続税上有利になる場合もあるため、注意が必要です。)
ここでは一例をご紹介させていただきました。他にも遺言を書いた方がよいケースとして、相続人がいない方、相続人が多い方、法定相続人以外に財産を残したり寄付をしたい方、相続人同士の仲が良くない方などがあります。
早めの対策を
相続対策について様々なご相談を受けてきましたが、お元気なうちに考えておくことがとても重要だと感じます。このご時世、いつ何が起こるかわかりません。あとでいいやと思っていると後悔してしまうかもしれません。まずはご自身のお考えや今のご状況を整理してみましょう。「少しでも多く家族に残してあげたい」「負担をかけないようにしたい」「自分が亡くなっても皆で仲良く協力して頑張ってほしい」少しでもそのような思いのある方は、早めの対策をお勧めします。どのように分けるのが最適か分からないという場合は、専門家にご相談いただくとよいでしょう。これまで築き上げてきた大切な財産をご自身のお考えに合わせて残せるようにしっかりと対策していきましょう。
また、相続対策に際して悩まれることがあればぜひ『オカネコ』をご活用ください。
『オカネコ』は、家計改善、資産運用、保険などお金に関するさまざまなアドバイスをワンストップで無料相談できる国内最大級のプラットフォームであり、どんな立場の人にも有効な「お金の問題解決」の機会を提供し続けています。
相続に関するお金の悩みも、お金のプロに何度でも無料で相談できます。
相続対策に関して、最初に何をすればよいかわからない方もぜひオカネコにご相談ください。
▼オカネコへのご相談はこちら
https://okane-kenko.jp/planner/2794?exclusive
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
