なぜ今、家族信託が注目されているのか?その背景とメリット (株式会社ファミトラ 2025.1.15)

近年、家族信託という言葉をよく耳にするようになりました。テレビや新聞、雑誌などのメディアでも取り上げられる機会が増え、多くの人々の関心を集めています。しかし、なぜ今、家族信託が注目を集めているのでしょうか?
その背景には、日本社会が直面している様々な課題があります。
この記事では、家族信託が注目されるようになった背景と、家族信託がもたらすメリットについて詳しく解説していきます。
家族信託が注目される背景
超高齢社会と認知症の増加

日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入しています。2024年の総務省統計局のデータによると、65歳以上の高齢者人口は3,625万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は29.3%に達しています。この数字は今後も増加し続け、2040年には高齢化率は37.7%(*1)に達すると予測されています。
*1:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来統計人口(令和5年推計)より
高齢化に伴い、認知症患者の数も急増しています。厚生労働省の推計によると、2025年には認知症患者数が約700万人に達すると予想されています。これは65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症となる計算です。
このような状況下で、もし認知症等で判断能力を喪失してしまった場合に、財産管理をどうするのかという問題が大きな社会課題となっています。家族信託は、この課題に対する有効な解決策の一つとして注目を集めています。
平均寿命と健康寿命の差
日本人の平均寿命は世界トップクラスですが、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)との間には大きな差があります。
2019年の厚生労働省の統計によると、平均寿命と健康寿命の差は、男性で約9年、女性で約12年です。
この差は、多くの人々が人生の最後の数年間を何らかの支援や介護を必要とする状態で過ごすことを意味しており、この期間の財産管理や生活の質の維持が大きな課題となっています。
資産凍結の問題
認知症などにより判断能力が低下した場合、本人名義の預金口座や不動産などの資産が凍結されてしまう可能性があります。これは、本人が契約行為を行う能力を失ったと判断された場合に、金融機関や取引先が資産の凍結や取引の停止を行うためです。
預金口座が凍結されると、日常生活に必要な支払いや資産の管理が困難になる場合があります。例えば、介護サービスの利用料や施設入所費用の支払いが滞る等です。
また、不動産を保有している場合には、その管理や売却が難しくなります。
家族信託は、このような資産凍結のリスクを回避し、本人の意思を尊重しながら円滑な財産管理を可能にする手段の一つです。
家族信託の主なメリット
家族信託が注目される背景を踏まえ、ここからは家族信託がもたらす具体的なメリットについて解説します。
1. 認知症になっても財産管理が可能
家族信託の最大のメリットは、財産を持っている人(委託者)が判断能力を喪失しても、財産をあらかじめ指定した人(受託者)に預けておくことで、柔軟な管理、運用、処分が可能になることです。
2. 柔軟な財産管理が可能
家族信託を組成する際には、財産を預ける人(委託者)があらかじめ、財産を預かる人(受託者)がどのように財産を管理し、どのような目的のために使用するかを、決めておきます。具体的には、信託契約書を作成し、その中で信託目的として記載します。
この信託目的は柔軟に定めることが可能で、成年後見制度と比較した際の家族信託の大きな利点の一つです。成年後見制度は裁判所が管轄しているため、後見人(財産を管理する人)の裁量が限られており、財産を預ける本人の意思を十分に反映することが難しい場合があります。
3. 財産の承継をスムーズに行える
家族信託には、生前の柔軟な財産管理に加え、逝去後に財産の承継をスムーズに行うことができる機能があります。
信託契約の中で、例えば「委託者(財産を預けた人)が亡くなった後は、自宅は長男に、現金は長女に」と定めておくことで、家族信託の対象とした財産については、遺言と同じような機能を得られ、相続手続きの簡素化にもつながります。
4. 信頼する家族が財産を管理できる
家族信託は、公的機関による監督を必要としない私的契約であるため、信頼する家族が財産の使い途や管理方法を決めることができ、プライバシーを守りやすいというメリットがあります。
成年後見制度では、家庭裁判所に財産の残高や管理状況等を定期的に報告する必要があります。
家族信託においても、帳簿等の作成が義務付けられていますが、法律上、提出義務があるのは財産を預けた人等の関係者のみです。
しかしながら、この公的機関への開示が不要であることがメリットである反面、近年、受託者(財産を預かる人)が信託財産を私的に流用する等のトラブルが増加しており、信託監督人等、客観的に信託財産の管理状況を確認する第三者を定めておくことがのぞましいとされています。
5. 長期的な財産管理が可能
家族信託は、委託者(財産を預けた人)の死後に財産を引き継ぐものの、その管理が難しい家族がいる場合、信託契約を終了させず、受託者(財産を預かる人)による管理や運用を継続することができます。
たとえば、同じく高齢である配偶者や、障がいのあるお子様等に財産を引き継がせたい場合です。
これは遺言では実現できない機能であり、単なる相続対策を超えた、家族の将来を見据えた財産管理を可能にします。
6. 様々な資産に対応可能
家族信託は、預金や自宅だけではなく、有価証券や自宅以外の不動産など、様々な種類の資産の管理に対応することができます。特に、賃貸不動産の管理において、家族信託は有効な手段となります。
例えば、所有者が認知症等になり、賃料の収受や大規模リフォームの検討が困難になった際、受託者がかわりに判断や手続きを行うことができます。
まとめ
家族信託が注目されている背景には、超高齢社会の到来、認知症患者の増加、平均寿命と健康寿命の差、資産凍結の問題など、日本社会が直面する様々な課題があります。
家族信託は、これらの課題に対する有効な解決策の一つとして、以下のようなメリットを提供します
- 認知症になっても財産管理が可能
- 柔軟な財産管理が可能
- 財産の承継をスムーズに行える
- 信頼する家族が財産を管理できる
- 長期的な財産管理が可能
- 様々な資産に対応可能
しかし、家族信託にはメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。例えば、組成に相応の費用がかかることや、受託者が大きな権限を持つが監督機能が弱いこと等です。また、家族信託は遺言機能を有することから、相続税等を考慮し承継内容を検討する必要があります。
家族信託の利用を検討する際は、自身の状況や家族の事情をよく考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、慎重に判断することが重要です。家族信託は、適切に活用することで、本人の意思を尊重しつつ、家族の未来を守る強力なツールとなります。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
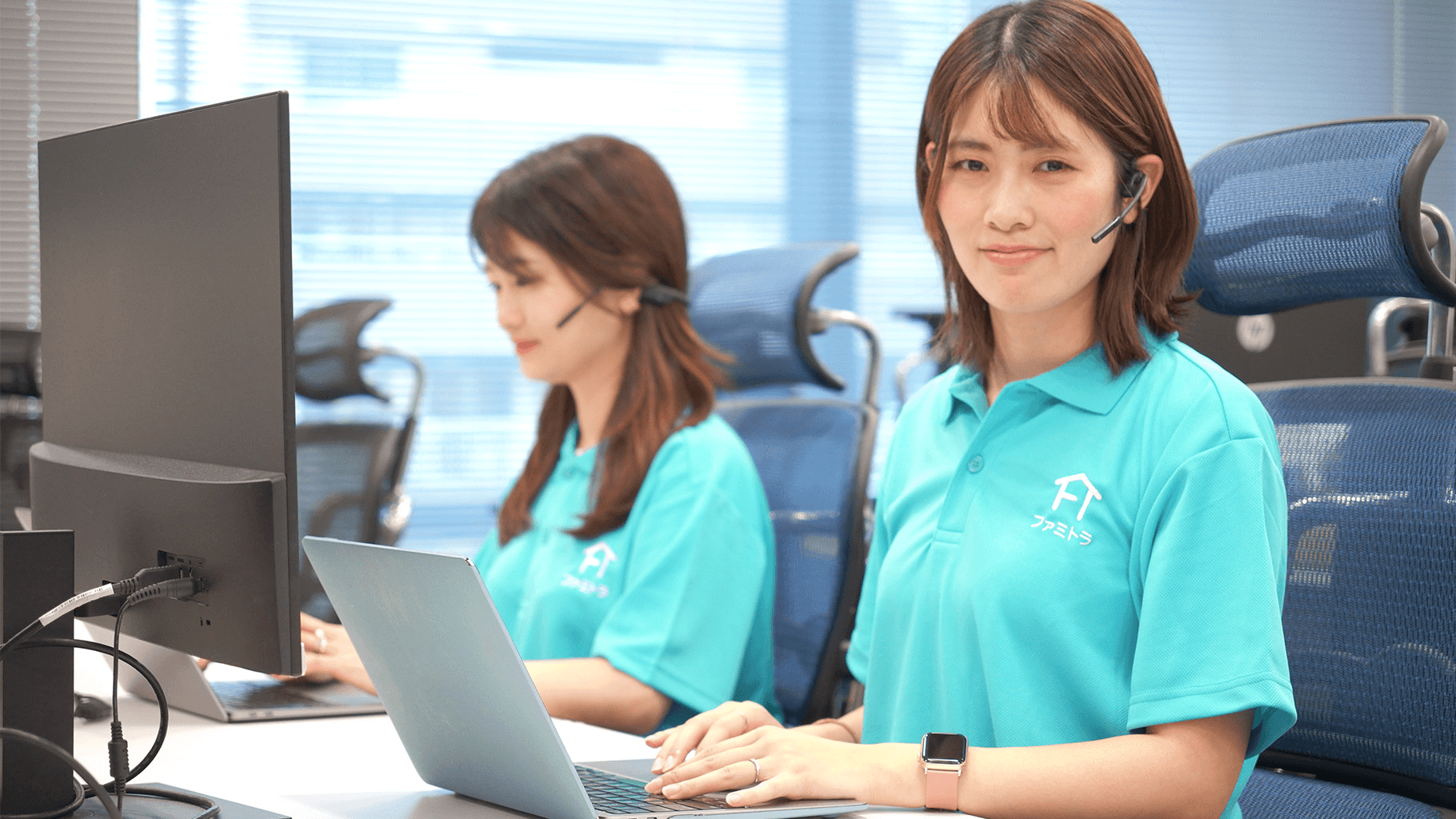
株式会社ファミトラ
- 対応地域
- 全国
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00
- アクセス
- 地下鉄「六本木一丁目」駅徒歩4分
- 得意分野
- 家族信託組成サポート・不動産相続