家族信託のしくみを徹底解説:委託者・受託者・受益者の役割 (株式会社ファミトラ 2025.2.4)

家族信託は高齢化社会において、認知症等による資産凍結リスクに対応する財産管理と、亡くなったあとの相続対策がひとつの契約で実現する新しい制度として注目されています。
しかし、その仕組みや関係者の役割については、まだ十分に理解されていないことも多いです。この記事では、家族信託の基本的な仕組みと、委託者、受託者、受益者のそれぞれの役割について詳しく解説します。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、信頼する家族に財産管理の権限を託す仕組みです。
認知症などを発症して判断能力が低下してしまった際に、その人の預金口座が凍結されてしまうことがあります。
判断能力が低下する前に、家族信託を利用して財産管理を家族に委託しておけば、預金口座の凍結を免れることができるのです。
家族信託の当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
委託者(いたくしゃ)
委託者は、自身が保有する財産の管理を、信頼する人にお願いして預ける人です。
誰に管理してもらいたいか、どの財産についてお願いしたいか、信託契約を締結したあと、実際にどのように財産を使ってほしいか等を決めるのは委託者になります。
委託者の主な役割
- 信託契約の締結:信託契約書を作成し、信頼できる受託者に財産の管理を託します。
- 財産の指定:どの財産を信託するかを決定します。
- 目的の設定:信託財産がどのように管理・運用されるべきか、その目的を明確にします。
- 信託財産の引き渡し:信託契約の締結後に、信託する財産を受託者に引き渡します。
受託者(じゅたくしゃ)
受託者は、委託者から依頼されて財産を管理・運用する人です。通常は家族が選ばれますが、委託者との間に信頼関係があれば、遠縁、友人、知人等の第三者でも受託者として選任できます。
受託者は信託目的に沿って財産の管理、運用、処分等を行い、その結果を定期的に後述する受益者に報告する義務があります。
受託者には善管注意義務および忠実義務など様々な義務が課せられており、責任を持って適切に管理、運用することが求められます。
受託者の主な役割
- 財産管理:信託された財産を適切に管理、運用、処分等します。
- 収支報告:定期的に受益者等に対して管理状況を報告します。
受益者(じゅえきしゃ)
受益者は、信託財産から生じる利益を享受する人です。また、この権利(信託財産から利益を受ける権利)を受益権といいます。
家族信託においては大半のケースで、契約当初は委託者が受益者を兼ねます(委託者兼受益者となります)。
委託者兼受益者が亡くなったあとは、受益者不在のため信託が終了するケースと、受益権を配偶者や子供などが引き継ぐケースがあります。
受益者の主な役割
- 利益享受:信託財産から生じる利益を享受します。自宅を信託する場合は引き続き居住する権利、金銭を自身の生活や医療のために使ってもらう権利がこれに当たります。
- 権利行使:受益者は、家族信託において大きな権限を持ちます。例えば、受益者は受託者に対し信託財産の管理状況について報告を求めたり、受託者を解任したりすることができます。
家族信託と他制度との違い
家族信託は成年後見制度や遺言とは異なる特徴があります。それぞれの違いについて簡単に説明します。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、判断能力が低下した人々が法的保護下で生活できるよう支援する制度です。この制度では家庭裁判所が後見人を選任し、その監督下で財産管理が行われます。一方で、家族信託では裁判所等の公的機関の関与なく、自主的な家族間の契約によって柔軟な財産管理が可能になります。
遺言との違い
自身が亡くなった後、財産を指定する人に分配するよう生きている間にあらかじめ指示できます。これを実現するのが遺言です。
つまり、遺言は遺言者が亡くなった瞬間に効力を発するため、生前の財産管理には効力がありません。
家族信託設定時のポイント
信頼できる受託者選び
家族信託は金銭や不動産といった財産の管理を任せるため、信頼できる家族を選ぶことが最も重要です。
また、その人に管理する能力があるか、管理を担う時間的余裕があるか等も、受託者選定の際の重要なポイントになります。
明確な契約内容
家族信託の契約書には、財産の管理を任せる委託者や信託財産から利益を受ける権利のある受益者が、判断能力を喪失した後に起こりうる事象を予測し、その際に受託者の指針となるような内容を明確な記載で盛り込むことが大切です。
法改正等への対応
信託契約を締結した後に、法律改正や外部環境により状況が変化することも考えられます。このため、信託契約の締結後も相談可能な専門家を見つけておくことがのぞましいです。
まとめ
家族信託は、高齢化社会における認知症等による資産凍結リスクに対応する財産管理の制度として有効ですが、設計の検討や組成の手続きには専門的な知識が必要になります。
また、家族信託は組成から受益者の死亡まで続くため、数十年という長期にわたり契約が継続するケースもあります。この間の環境変化等に柔軟に対応できるよう、準備をしておくことが大切です。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
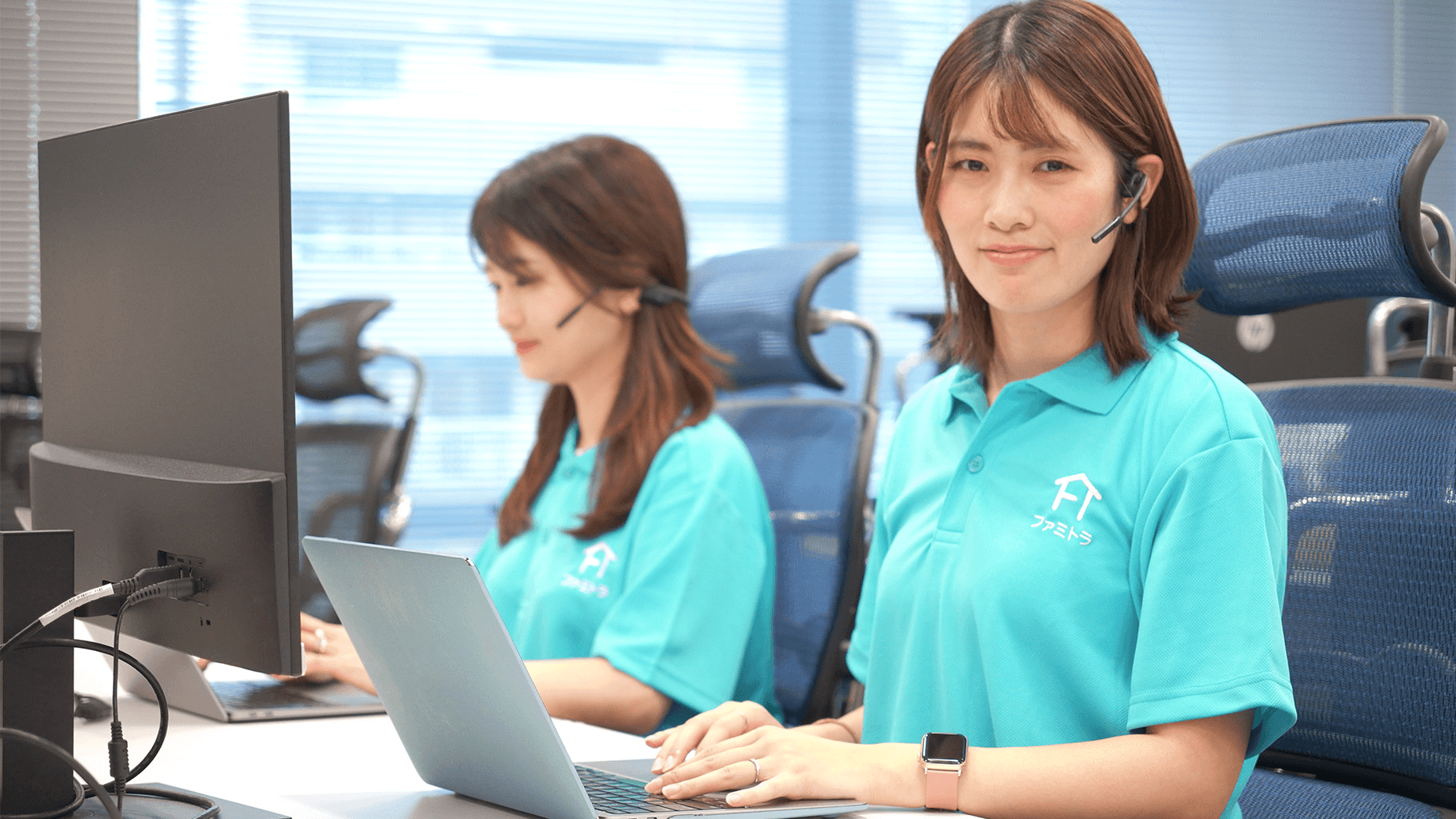
株式会社ファミトラ
- 対応地域
- 全国
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00
- アクセス
- 地下鉄「六本木一丁目」駅徒歩4分
- 得意分野
- 家族信託組成サポート・不動産相続