家族信託の具体的な活用例と検討をおすすめするケース (株式会社ファミトラ 2025.4.10)

家族信託は、高齢化社会における財産管理や相続対策として注目を集めている制度です。しかし、どのような場面で活用できるのか、具体的にイメージが思い浮かばない方も多いでしょう。この記事では、家族信託の具体的な活用例と、特に検討をおすすめするケースについて詳しく解説します。
1. 認知症に備えるケース
認知症は高齢化社会の大きな課題の一つです。家族信託は、認知症等により財産の管理ができなくなってしまうリスクに対する有効な解決策です。
具体例:父親の認知症に備える
70歳の父親Aさんは、自宅と賃貸アパート3棟を所有しています。Aさんには50歳の長男Bさんがいます。Aさんは将来の認知症に備えて、財産管理を長男Bさんに任せたいと考えており、以下のような家族信託の設定を検討しています。
- 委託者:Aさん(父親)
- 受託者:Bさん(長男)
- 受益者:Aさん(父親)
- 信託財産:自宅と賃貸アパート3棟
信託契約では、以下のような内容を定めることができます:
- 家族信託を契約し、以降はBさんが全面的に信託財産の管理を行う
- 賃貸アパートの収入は不動産の管理やリフォームの支払いのほか、Aさんの生活費や医療費に充てる
- 必要に応じて、信託財産を一部売却し、Aさんの生活費や医療費、介護費用に充てる
このような信託を設定しておくことで、Aさんの判断能力の有無にかかわらず、Bさんが適切に財産管理を行い、Aさんの生活を支えることができます。
2. 障がいのある子の将来を考えるケース
障がいのあるお子様の将来を心配する親御さんにとって、家族信託は有効な選択肢となります
具体例:親亡きあとの障がいのある子の財産管理
80歳の母親Cさんには、50歳の知的障がいのある長男Dさんと、45歳の次男Eさんがいます。Cさんは、自分が亡くなった後はDさんに相応の現金を遺したいと考えていますが、知的障がいがあるため、Dさん自身では管理が困難であることを懸念しています。
この場合、以下のような家族信託を設定することができます:
- 委託者:Cさん(母親)
- 受託者:Eさん(次男)
- 当初受益者:Cさん(母親)
- 第二受益者:Dさん(障がいのある長男)
- 信託財産:Cさんの預貯金
信託契約では、以下のような内容を定めることができます:
- Cさん存命中は、信託財産からCさんの生活費や医療費を支払う
民法上の扶養の範囲でDさんの生活費や医療費を支払うことも可能
- Cさんの逝去後は、Dさんの医療費や介護費用を信託財産から支払う
- CさんとDさんの両名が亡くなったあとは、Eさんが財産を承継する
このような信託を設定しておくことで、親亡き後にDさんが受け取った財産を、引き続き家族が管理することができます。
3.不動産の共有トラブルを未然に防ぐケース
複数の相続人で不動産を共有すると、意思決定や管理で問題が生じることがあります。家族信託は、このような不動産の共有トラブルを未然に防ぐ有効な手段となります。
具体例:賃貸アパートの共有トラブルを防ぐ
80歳の父親Fさんは、賃貸アパートを一棟所有しています。Fさんには3人の子供(長男Gさん、長女Hさん、次女Iさん)がいます。Fさんは、自身の死後、3人の子供たちが賃貸アパートの運営でもめることを心配しています。
この場合、以下のような家族信託を設定することができます:
- 委託者:Fさん(父親)
- 受託者:Gさん(長男)
- 当初受益者:Fさん
- 第二受益者:Gさん、Hさん、Iさん(3人の子)
- 信託財産:賃貸アパート一棟
信託契約では、以下のような内容を定めることができます:
- 長男Gさんが賃貸アパートを一括管理する
- 父親Fさんの存命中は、賃貸収入はFさんのために使う
- Fさん逝去後は、賃貸収入は3人の子どもたちで等分に分配するが、管理は引き続きGさんが行う
- アパートの大規模修繕や建て替えは、Gさんが判断して実行する
- 将来的にアパートを売却する場合の手続きはGさんが行い、売却代金は3人の子どもたちで等分に分配する
このような信託を設定することで、不動産の共有に伴うトラブルを防ぐ効果が期待でき、スムーズな資産承継が可能になります。
4.事業承継対策として活用するケース
家族信託は、中小企業のオーナー事業承継を円滑に進めるための手段としても注目されています。
具体例:会社の経営を円滑にしながら、次世代に承継する
75歳の中小企業オーナーJさんは、最近もの忘れが増えてきており、認知症等により会社の経営が滞ることを懸念しています。
Jさんにはひとり息子のKさんがおり、将来的には会社経営を任せたいと考えていますが、Kさんは遅くできた子であるため、まだ25歳と若く、今すぐ任せるのは早いと考えています。
自分がもし認知症になった場合には、Kさんが会社の経営に慣れるまで、専務として起業時から会社を支えてくれている55歳のLさんに経営判断を任せたいと考えています。
この場合、以下のような家族信託を設定することができます:
- 委託者:Jさん(社長)
- 受託者:Lさん(専務)
- 当初受益者:Jさん(社長)
- 第二受益者:Kさん(社長の息子)
- 信託財産:Jさんが保有する自社株式
- 信託終了時期:Kさん(社長の息子)が40際に達した時
信託契約では、たとえば以下のような内容を定めることができます:
- 信託契約中はLさんが議決権を行使する
- Jさんの死後も、Kさんが40歳に達するまではLさんが議決権を行使する
- Kさんが40歳に達すると信託が終了し、Kさんが株式を取得する
このような信託を設定することで、会社の円滑な経営を維持しつつ、事業承継を実現することができます。
※Kさんが40歳に達した際にJさんが存命であった場合の対応や、Lさんへの受託者報酬の支払いなど、この信託の設計には多くのリスクや検討事項があるため、専門家に相談することをおすすめします。
家族信託の検討をおすすめするケース
以上の具体例を踏まえ、特に家族信託の検討をおすすめするケースをまとめると、以下のようになります:
- 認知症などの判断能力低下に備えたい場合
- 障がいのあるお子さんの将来の財産管理を実現したい場合
- 不動産の共有トラブルを回避したい場合
- 中小企業の事業承継を円滑に進めたい場合
これらのケースに該当する方は、家族信託の活用を真剣に検討する価値があるでしょう。一方で、家族信託にはデメリットもあるため、専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。
まとめ
家族信託は柔軟な設計が可能なため、上記のような様々な場面で活用できる制度です。特に、従来の相続対策や成年後見制度では対応が難しかった課題に対して、有効な解決策となる可能性があります。
ただし、家族信託の設定には専門的な知識が必要であり、また、家族信託において財産を預かる役割を担う受託者には、信託財産の管理に関する責任も伴います。そのため、家族信託を組成する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家族信託は、大切な財産を守り、次世代に引き継ぐためにたいへん有効な方法です。
ご自身や大切な家族の将来のために、家族信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
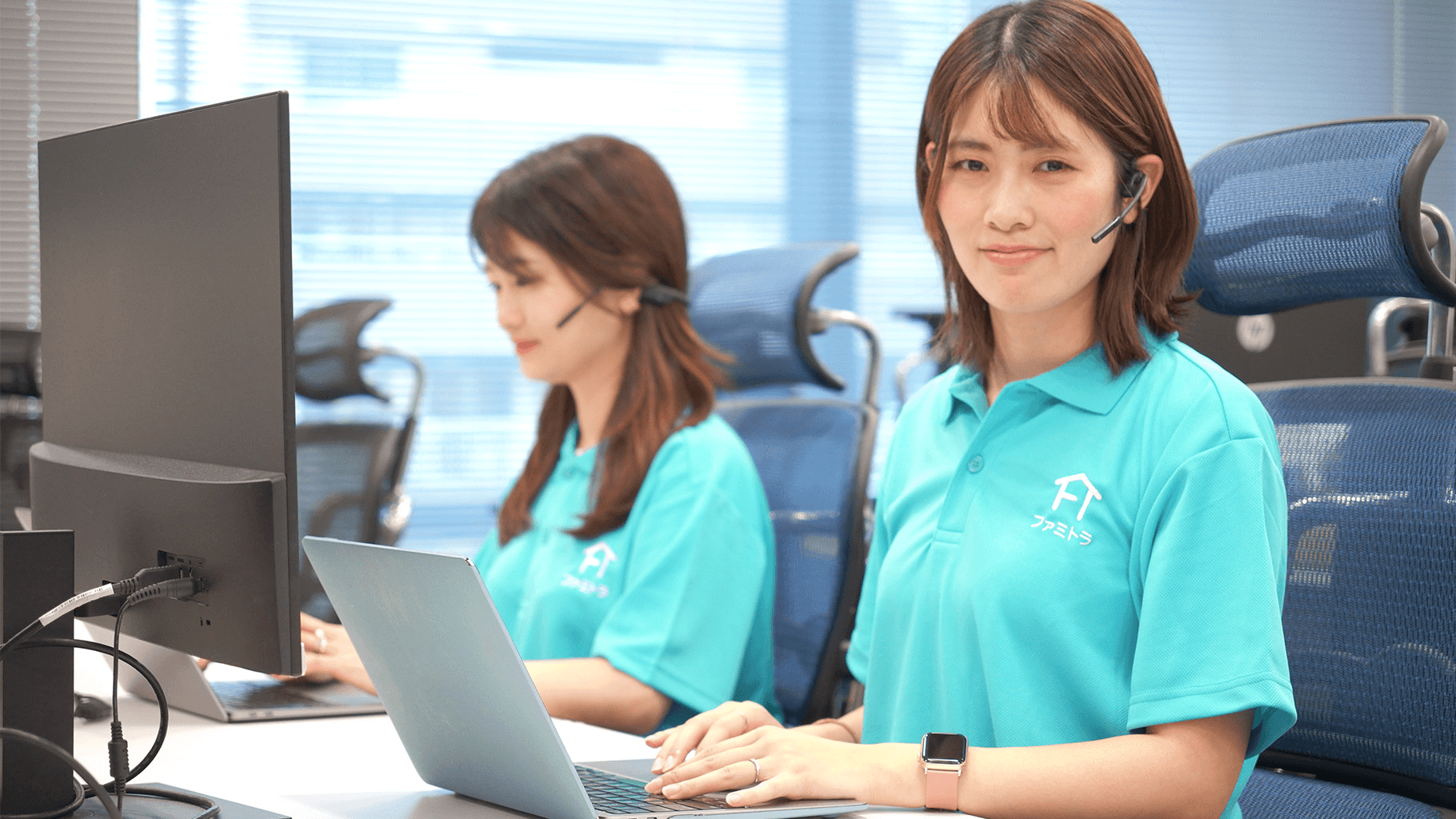
株式会社ファミトラ
- 対応地域
- 全国
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00
- アクセス
- 地下鉄「六本木一丁目」駅徒歩4分
- 得意分野
- 家族信託組成サポート・不動産相続