家族の未来も、ふるさとへの恩返しも。ある男性が選んだ遺贈寄付という決断 (一般社団法人日本承継寄付協会 2025.4.1)
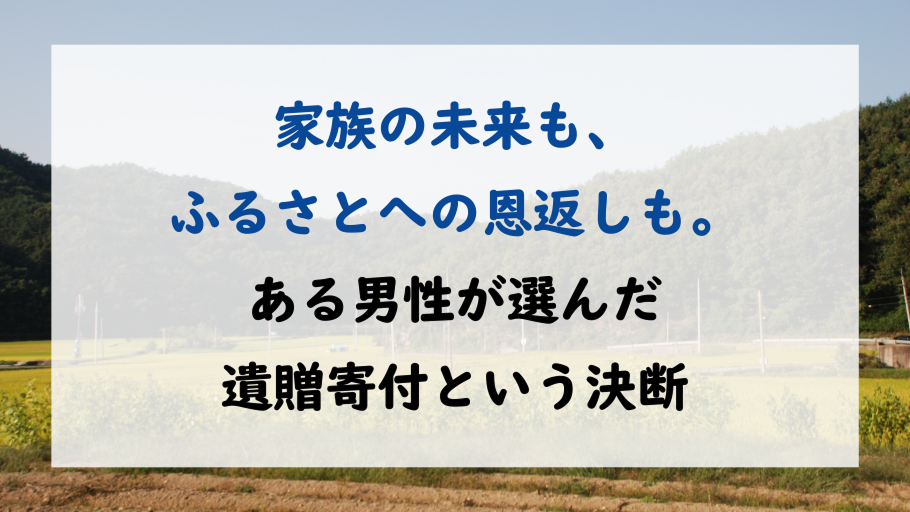
「生まれ育った地域に恩返しをしたい」 ─ ある男性の想い

「自分が生まれ育った地域に、少しでもお返しができたら……。」
そんな思いを胸に、一人の男性が選んだのは遺贈寄付という選択でした。
生まれ育った地域を離れ、違う土地で仕事や家庭を築く方も多いのではないでしょうか。
ふるさとのことを気にかけつつも、日々の忙しさの中では具体的に「どうやって恩返しをするか」を考える機会はなかなか訪れません。
「いろんなことで助けてもらった。その恩を、何かしらの形で返したい。」
人生の終盤に差し掛かったとき、男性の中でその思いはますます強くなっていきました。
家族と社会、どちらも支える相続の形
「家族には一定程度残せればいい。それでなんとかなるだろう。」
家族の暮らしを守ることは大前提。
しかし、それと同時に「ふるさとへの恩返しという遺志」をつなぎたい思いもありました。
自分がいなくなったあとも、遺志を未来へつなぐ方法を探し始めた結果、遺贈寄付という手段に辿り着きました。
単なる財産の相続だけではなく、遺産の一部を未来のための活動に使ってもらうことで、地域社会へ恩返しをする。
その方法として挙げられたのが「遺贈寄付」だったのです。
遺贈寄付という新しい選択肢
遺贈寄付とは、亡くなった後に財産の一部や全部をNPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体に寄付することです。
近年、日本でも少しずつ認知され始めていますが、いまだに「遺産=家族にすべて相続」という固定観念が根強く残っています。
しかし、彼のように「自分が助けてもらった社会に恩返しをしたい」と考える人にとって、遺贈寄付は大きな可能性を持つ選択肢なのです。
遺贈寄付をするためには、適切な準備が必要です。
・相続人と財産を把握する
・寄付先を決める(NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体など)
・遺言書を作成する(確実に執行されるように公正証書遺言がおすすめ)
これらの準備をスムーズに進めるためには、専門家(行政書士や司法書士、金融機関など)と相談しながら進めると安心です。
「遺言書といっても大袈裟なものではなく、自分で決めた遺贈寄付をどう担保するか」
彼はそう考え、遺言書の中にその想いをしっかりと反映させました。
未来へつなぐ、自分らしい遺産の活かし方

遺贈寄付とは、お金持ちだけのものでもなく、単なる財産の分配でもありません。
人生の中で受けた恩を未来に還元し、次世代へつなぐ手段でもあります。
彼のように、「家族にはしっかりと財産を残しつつ、生前に使いきれなかった財産を社会に役立てたい」と考える人にとって、遺贈寄付は有力な選択肢のひとつとなるでしょう。
「ふるさとや社会からは色々な仕組みで助けてもらってきた。だからこそ遺贈という形で想いをつなげていきたい」
遺贈寄付を通じて、あなたの想いは未来の誰かの力になり、社会を支える大切な一歩となるかもしれません。
あなたも、「大切な人を守る」×「社会へ想いを託す」 という新しい相続の形を考えてみませんか?
上記のストーリーを動画でご覧いただけます。
遺贈寄付について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
▼遺贈寄付の方法が知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_7866.html
▼遺贈寄付を含む遺言書の書き方を知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8088.html
▼遺贈寄付のメリットを知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8001.html
▼遺贈寄付の体験談をさらに知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8571.html
▼寄付先を知りたい方は
日本承継寄付協会が発行する遺贈寄付情報誌「えんギフト」を無料でお取り寄せいただけます
https://www.izo.or.jp/service/gift.html
監修:一般社団法人日本承継寄付協会
執筆:小笠原かすみ
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
