公正証書遺言とは何か、自筆証書遺言との違いなどをわかりやすく解説 (辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2025.4.22)
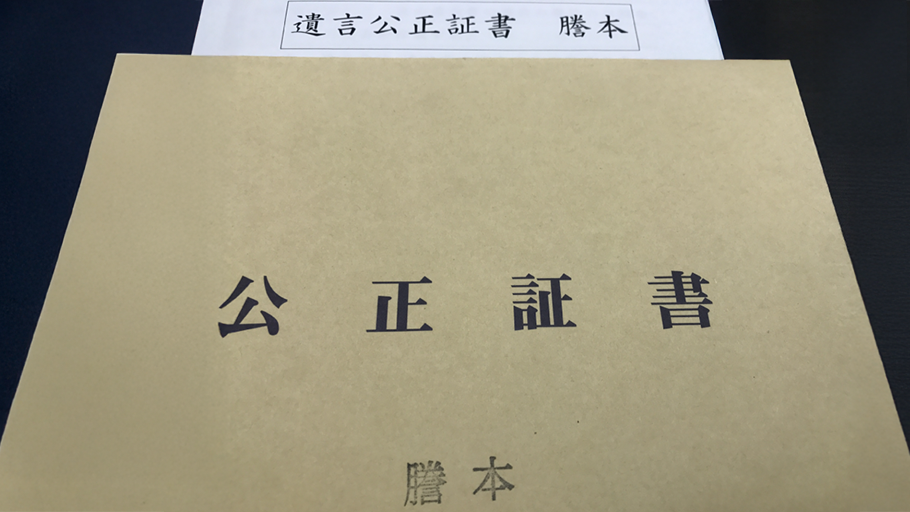
公正証書遺言とは何かわかりやすく解説
公正証書遺言とは、公証人立ち会いのもと、公証役場で作成された遺言書です。自筆証書遺言と比べ、より確実に効力を発揮できる遺言書として利用されています。
遺言書を作成する費用がかかるものの、公証役場で保管されるため、紛失などのリスクが低く、家庭裁判所での検認も不要となるため、相続人にとってもメリットのある遺言書です。
自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言は自分で記載した遺言書です。
自分で作成するため、遺言書の作成方法などを調べる必要があります。内容に不備があった場合、効力がなくなり、相続人の間でトラブルに発展する可能性があります。
また、自筆証書遺言は遺言者が死亡した際、家庭裁判所での検認が必要となります。なお、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットとデメリットについて解説します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証人によって作成されるため、遺言書の不備などで効力がなくなる可能性がほとんどありません。改ざんなどの可能性も低いため、信頼性の高い遺言書を作成することができます。
また、遺言者が死亡した際、家庭裁判所での検認が不要です。相続人の負担を減らすこともできます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は作成に費用がかかります。費用は公証人手数料令によって定められており、遺言に記載する財産の価額によって異なります。
また、財産の内容を証人2名に公開する必要があります。財産を隠しておきたい方にとってはデメリットとなります。
公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成方法について解説します。
遺言書作成に必要な情報や必要書類をまとめる
自分が保有している財産や誰が相続人になるのかなどを洗い出し、財産を誰にどのような割合で相続・遺贈させたいのかメモを作成しておきます。
また、公正証書遺言の作成について公証人へ相談した際に伝えられた必要書類も準備しておきます。
公証人と遺言内容について相談する
財産の分割方針に関するメモや必要書類を公証人へ提出し、その内容を元に公証人が遺言書の案を作成してくれます。
内容を確認し、問題があれば修正を依頼、問題がなければ遺言書の内容を確定します。相談の段階では証人の立ち合いは不要です。
公証人の相談は何度でも無料です。ただし、相続税を抑えたいなど個別の事情を考慮した分割方針の相談は公証人へはできません。各相談は専門家へ依頼しましょう。
公正証書遺言の作成日を決める
公正証書遺言の案に納得した場合、公正証書遺言を作成する日を決めます。公証人、証人、遺言者の予定を合わせ、予約を行います。
一般的には公証役場で作成しますが、自宅や病院で作成することもできます。
公正証書遺言の作成してもらう
公正証書遺言を作成する当日、遺言者が遺言の内容を口頭で読み上げます。その後、事前に作成した公正証書遺言案を遺言者および証人2名が確認します。
問題なければ、遺言者および証人2名、公証人が遺言公正証書の原本に署名と押印を行い、公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言に必要な書類は以下の通りです。なお、場合によって他の書類も必要となる可能性があります。詳細は公証役場へお問い合わせください。
- 発行から3か月以内の遺言者本人の印鑑登録証明書(運転免許証やマイナンバーカードで代替可能)
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 遺言者の戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票など住所の記載のあるもの。法人の場合は登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産を相続させる場合、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金等を相続させる場合、預貯金通帳等またはその通帳のコピー
- 遺言者の方で証人を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの
- 遺言執行者を指定する場合、遺言執行者の名前、住所、生年月日、職業のメモ
公正証書遺言は見つけてもらわないと効力を発揮しない
公正証書遺言の作成者が亡くなったとしても公証役場から相続人へ通知は行われません。そのため、相続人へ遺言書があることを事前に伝えておくことが大切です。
口頭で公証役場に遺言書があることを伝える、公正証書遺言の正本または謄本を自宅に置いておくなどの方法があります。
また、遺言執行者を指定している場合、遺言執行者は相続人へ遺言の内容を通知する義務を負います。専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合、専門家を遺言執行者とし、相続人へ通知するという方法もあります。
相続人が遺言書の有無を確認することもできる
遺言書の作成者が亡くなった場合、相続人など法律上の利害関係があれば、公証役場で遺言書の有無を検索することができます。全国の公証役場を一斉に検索できるため、自宅近くの公証役場へ行けば、遺言書の有無を無料で確認できます。
なお、遺言書の検索には遺言者の死亡を証明する資料や利害関係を証明する書類、本人確認資料などが必要です。
相続人へ通知されるようにするには自筆証書遺言を法務局で保管する
遺言書の作成者が亡くなった際に相続人へ遺言書があることを通知したい場合、自筆証書遺言書保管制度を活用します。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度で、一定の条件の下、亡くなった際に関係相続人等へ遺言書が遺言書保管所に保管されていることが通知されます。
相続について生前に準備するなら『better相続手続きガイド』などをご利用ください
公正証書遺言を作成することで遺言者の意思を反映させることができ、相続人の間でトラブルが起こる可能性も小さくすることができます。
遺言者の作成だけでなく、生前贈与などを活用した相続税対策、財産や利用しているサービスの整理なども相続対策に有効です。
相続が発生した際、どのような手続きが必要になるのか、生前にどのようなことをすれば相続人の手間や時間を削減できるのか考えたい方はぜひ弊社が開発した『better相続手続きガイド』をご活用ください。
また、相続発生後、専門家へ手続きを依頼すると数万円~数十万円の費用がかかるため、相続した財産が減ってしまう可能性があります。
『better相続申告』や『better相続登記』をご活用いただくと、相続人ご自身で簡単に相続税申告や相続登記ができるため、専門家へ依頼する費用を抑えることができます。相続人となる方へご紹介いただけますと幸いです。
(1)better相続手続きガイド
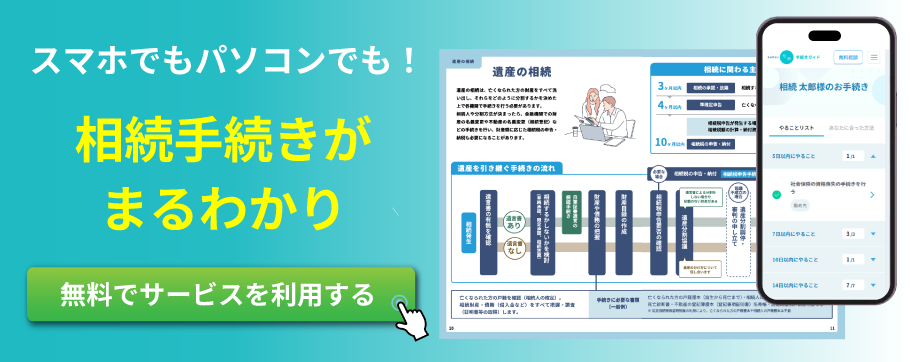
「いつまでに何をするのか」「書類は何が必要?」そのようなお悩みを解決する無料のWEBサービスです。
簡単な診断に回答すると必要な相続手続きをリストアップ。役所以外の手続きも網羅しているので抜け漏れなく相続手続きを進められます。
手続きの進め方や必要資料なども詳しく解説している他、将来の相続に向けた対策などのご相談も無料で行えます。
パソコンやスマホはもちろん、資料を印刷して利用することもできますので、紙で確認したい方にもおすすめです。
(2) better相続申告

相続税の申告を自分で簡単に完結できるWEBサービスです。
財産の洗い出しから必要資料のリストアップ、財産・土地の評価、申告書の作成・提出手順までこれ一つで完結します。
詳しい解説をシステム内に用意しているため、初めての方でも迷わずに手続きを進められます。
税理士へ依頼すると数十~数百万円かかる費用を大きく抑えられます。
無料でお試しいただけますので、まずは自分で申告できるかご確認ください。
自分で手続きを進めるのが難しい場合は税理士へ依頼することも可能です。
弊社が紹介する税理士へ依頼した場合はシステム利用料をご返金します。
(3)better相続登記
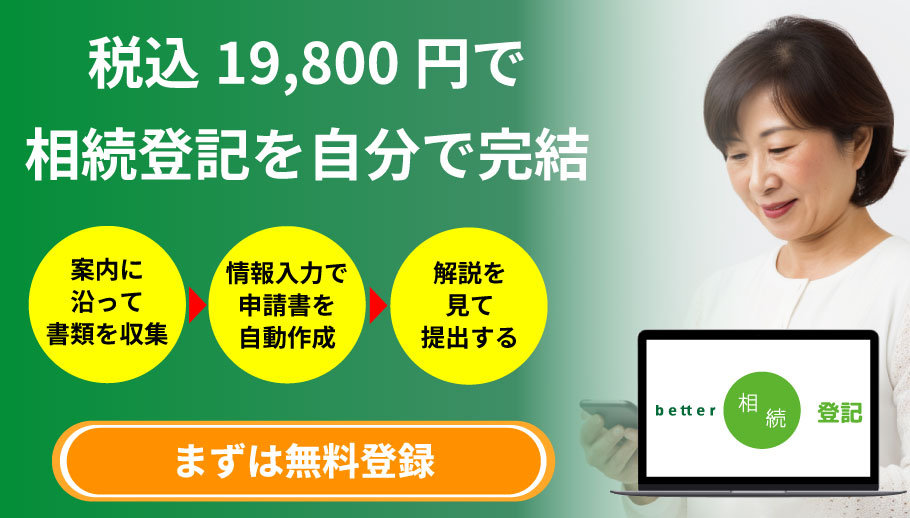
相続した不動産の名義変更を誰でも簡単に、自分で行えるWEBサービスです。
収集書類のリストアップ、登記申請書や遺産分割協議書の作成、申請手順までこれひとつで完結します。
システム内に詳しい解説を用意しているため、初めての方も迷わずに手続きを進められます。
2024年4月に相続登記が義務化されたため、まだ名義変更していない不動産がある方もぜひご利用ください。
司法書士に相続登記を依頼する費用を数万~十数万円抑えられます。
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社 で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
