遺贈寄付って本当に大丈夫?その仕組みと活用ポイントを専門家が解説
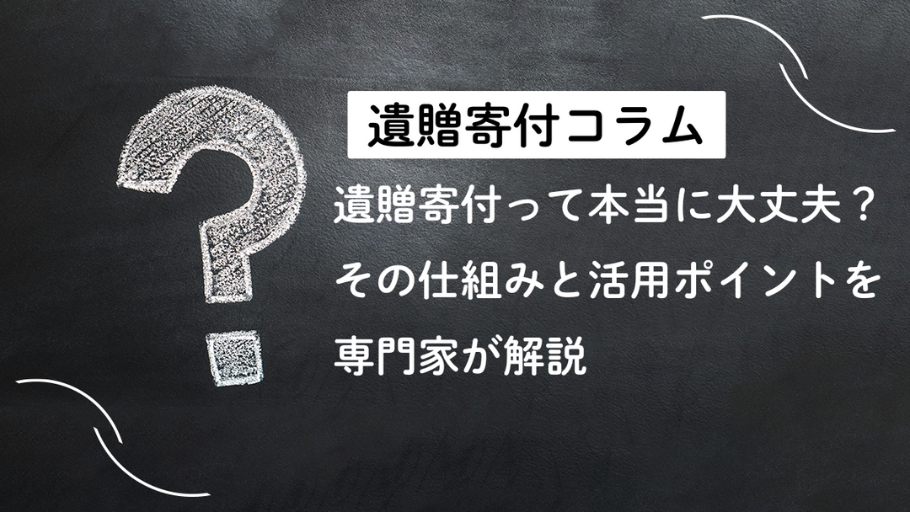
遺贈寄付は怪しい仕組み?
ここ数年で、「遺贈寄付」という言葉を耳にする機会が増えてきました。実際にこの制度を活用する方も、少しずつ増加傾向にあります。
しかしながら、「遺贈寄付って信頼できる制度なの?」「トラブルに巻き込まれない?」と、不安に思う方がいるのも事実です。
そこで本記事では、遺贈寄付という仕組みの基本から、メリットや注意点まで、幅広くご紹介します。
まず、疑問を持たれている方に向けて、遺贈寄付の概要を簡単にお伝えします。
遺贈寄付とは、遺言によって、自分の財産の一部または全てをNPO法人、学校法人、自治体などに寄付することを指します。寄付先はご自身の判断で自由に選べるため、関心ある社会課題や応援したい活動に対して意思を反映できます。
きちんと調べて信頼できる団体を選べば、その寄付は確実に社会に役立つ使われ方をするでしょう。
とはいえ、寄付や投資には詐欺的な手口が存在するのも事実です。特に高齢者を狙った悪質なケースもあるため、細心の注意が必要です。
遺贈寄付を安全に行うには、相続関連の経験が豊富な専門家(行政書士、弁護士、司法書士、信託銀行など)への相談が有効です。「この人なら信頼できる」と思える方にお願いしましょう。
また、情報収集も重要です。当協会が発行している遺贈寄付情報誌「えんギフト」では、信頼性の高い情報をわかりやすくまとめています。冊子は無料でお届けしていますので、ご希望の方はぜひお気軽にご請求ください。
えんギフトのご請求はこちら
制度への理解を深め、段階を踏んで進めていけば、遺贈寄付は決して怪しいものではありません。あなたの想いが、次の誰かへと引き継がれていく仕組みです。
もちろん、最終的に遺贈寄付を行うかどうかの判断はご自身次第です。無理をせず、この記事がその判断の一助となれば幸いです。
遺贈寄付を行うメリット

遺贈寄付には、社会的意義だけでなく、実用的な利点も多数あります。ここではその主なメリットをご紹介します。
■財産の使途を自分で決められるようになる
寄付先はご本人が選ぶため、「この団体の活動を支えたい」「この課題に取り組む人を応援したい」といった想いを形にできます。
■少額からでも寄付ができる
「大きな財産がないとできないのでは?」と思われがちですが、実際には少額でも遺贈寄付は可能です。相続人に財産を残しつつ、一部だけを社会に役立てることもできます。
■老後資金の心配がいらない
遺贈寄付は、亡くなった後に残った財産から行うため、日常の生活資金や老後資金に影響を与えません。遺言書は後から変更も可能なので、状況に応じて柔軟に調整できます。
■節税効果がある場合も
財産を相続するときに発生する相続税は遺産総額に対して課税されるのではなく、遺贈寄付をした財産は非課税となり、その結果として課税される財産が減る分、相続税が減少します。
遺贈寄付を行うことで、遺贈した財産は相続税の課税対象にならず、結果的に節税に繋がります。ただし、その寄付が相続税を不当に減少するために行われた行為とみなされると(=相続税逃れ)、遺贈を受けた法人を個人とみなして相続税が課税されます。
■社会貢献に繋がる
実際の遺贈寄付の理由として多いのが、「社会に恩返しがしたい」「誰かの役に立ちたい」といった気持ちです。遺贈寄付によって、人生の最後に大きな社会的価値を残すことができます。
■後世に想いや名前が残せる
感謝状や銘板、オリジナル基金などを通して、寄付者の名前や想いが後世に残る仕組みを整えている団体もあります。
■家族や周りの人に誇りに思ってもらえる
遺贈寄付は、残された家族にとっても「誇れる行動」として受け止められることがあります。当協会が行った調査では、8割の相続人が遺贈寄付を肯定的に受け止めていました。
遺贈寄付を行う際の注意点

ここでは、遺贈寄付を検討する際に押さえておきたいポイントを整理します。
■遺留分
遺贈寄付を行う際には、遺留分についても理解した上で寄付金額を考えておく必要があります。
配偶者や子ども等は法律で定められた額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。遺贈寄付では、遺留分を超えて寄付をすることも可能ですが、その場合、配偶者や子どもとトラブルになってしまう可能性が少なからずあります。
自身の財産の遺留分については事前に専門家と確認しておくことをオススメします。
■不動産や有価証券など現物の寄付
また、財産として不動産や有価証券など現物の寄付を検討されている方は、そのままだと寄付ができない可能性があるため注意が必要です。
不動産や有価証券は現物のまま寄付できるケースが少なく、不動産の遺贈寄付もできますが、その場合は遺言執行者もしくは寄付先側で売却されます。
不動産や有価証券に限らず、現物の寄付を行う際は、トラブルを避け、希望通りに遺贈をするためにも事前に寄付先に相談をしておきましょう。
■みなし譲渡税
不動産や株式を換価して遺贈寄付を行う場合、寄付先団体ではなく相続人に課税されてしまうおそれがあります。具体的には、換価する不動産や株式の含み益に対して課税が行われ、これを「みなし譲渡課税」と言います。
課税金額等によってはトラブルになってしまう可能性もありますので、不動産や株式を換価して遺贈寄付を行う場合は慎重に検討を進める必要があります。
事前に専門家と寄付先と協議の上、寄付先団体が税金を納めることができるるように遺言書を作成しておくのがおすめです。
まとめ
遺贈寄付という制度は、社会貢献の手段としてだけでなく、ご自身の想いを形にする方法でもあります。ですが、「制度がよく分からない」「本当に信頼できるのか」といった不安があるのも自然なことです。
まずは信頼できる情報に触れること、次に信頼できる人に相談することが、第一歩となります。
また、遺贈寄付は数百万円や数千万円といった大金だけでなく、1万円などの額からでも可能です。身構えず、できる範囲から始めてみるのも一つの方法です。
今回紹介した遺贈寄付のメリットや注意点を踏まえて、遺贈寄付を行うかどうか検討してみてください。
遺贈寄付について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
▼遺贈寄付の方法が知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_7866.html
▼遺贈寄付を含む遺言書の書き方を知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8088.html
▼遺贈寄付のメリットを知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8001.html
▼遺贈寄付の体験談をさらに知りたい方は
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_8571.html
▼遺贈寄付のQ&A
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_9748.html
▼【実態調査2024】「遺贈寄付、知ってはいるけど…」8割が実行に踏み切れない理由とは?
https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_10249.html
監修:一般社団法人日本承継寄付協会
執筆:藤田大地
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。

一般社団法人 日本承継寄付協会
- 対応地域
- 全国
- 営業時間
- 午前9:00-午後6:00(土日祝除く)
- アクセス
- 東京都文京区小石川2丁目3番4号 第一川田ビル7階
- 得意分野
- 遺贈寄付